連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」(6)
2021年12月11日~17日、全国24のアートハウス(ミニシアター)で同時開催された連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」。
監督や脚本家、製作者、編集者等、多彩な講師陣による7日間のトークの記録を連載します。

連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」
第6夜 2021年12月16日(木)
連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」第6夜は、ジャン・ルーシュとエドガール・モランによる『ある夏の記録』を上映。
講師は、東北を拠点に、岩手県陸前高田に暮らす人びとの営みや、変わりゆく風景を記録してきた映像作家の小森はるかさんと、多くの媒体で映画評やコラムを連載され、映画パンフレットや小雑誌『映画横丁』などの編集を手がけるエディター/ライターの月永理絵さん。小森さんの作品や制作手法にも触れながら、「カメラで真実を撮ること」について対話が重ねられました。
いい意味ですごく欲張りな映画
小森 まず、『ある夏の記録』を選んだきっかけについて触れたいと思います。2012年に演出家の高山明さんが主宰するPortBの『REFERENDUM – 国民投票プロジェクト』という作品をお手伝いさせてもらいました。全国の中学生に「いま一番ほしいものはなんですか」「総理大臣になったら何がしたいですか」といった一問一答のインタビューを行って、その映像をもとにつくられた作品です。そのインタビューの下敷きになったのが、1966年に作られたTBSの「あなたは…」というドキュメンタリー番組で、「あなたは幸福ですか」という質問を街頭で市民に投げかけて撮られた番組だと聞きました。ディレクターに萩元晴彦と村木良彦が、構成に寺山修司が参加しています。さらに、その番組がフランスの映画に影響を受けてつくられたという話を聞いたんですが、タイトルや監督を忘れてしまって。今回『ある夏の記録』の話を聞いて「それだ」と記憶が繋がって、選ばせてもらいました。
本作も、おそらく最初は街頭でインタビューをしていくはずだったと思うんです。だけど、なかなか話が聞けなかったり、カメラも距離感があったりしてうまくいかない。その後、車の修理屋さんのようなご夫婦が出てきてやっと話を聞けたと思ったものの、その夫婦は事前にインタビューを受けてくれることが決まっていた人で、よく見るとマイクも向けていません。その後は、もはや部屋の中で話を聞いている。話を聞く場の設定が変わることで、カメラが入っていける場所もどんどん変わっていきます。プロセス自体を作品に含み込むことは最初から想定して撮られたのだと思いますが、そのことに足をすくわれていないというか、カメラの前だけでなく、周囲で起きることに神経をはっていて、それもまた映画の中に持ち込んでいる。いい意味ですごく欲張りに作っている映画で、そういう作り方に学ぶところがありましたし、自分にはできないなという驚きがありました。

ジャン・ルーシュの一貫した制作手法
小森 最後、映画に撮られた人たちが試写を観て、好き勝手に言うシーンによって、いままで観ていたものが全部持っていかれてしまうような映画になっていると思うんですが、本作の監督のひとりであるジャン・ルーシュは、被写体となる人たちに撮った映像を見せてフィードバックを得ながらつくる方法を積極的に取り入れていた作家です。民族誌映画をたくさん残した人類学者としても知られていて、主にフランス領地だった西アフリカのニジェールで、異なる文化を持っている人たちにカメラを向けてきました。
『大河での戦い』というカバ狩りの儀礼を記録した作品をニジェールの人たちに見せたときに、「カバが少ししか出てこないじゃないか」「音楽をつけたらカバが逃げちゃうじゃないか」といった批判を受けたというエピソードがあるんですが、ルーシュはそれが嬉しかったようで、「それ以降音楽をつけるのはやめたんだ」ってインタビューで話しています。『ある夏の記録』の最後の場面にも重なってくると思います。撮られた人と撮った人の関係を対等に、対等にはならないんですけど、ルーシュは対等にしたいと考えて被写体に映像を見せる手法を取り入れていたと思っていて、そのことが、私がルーシュに興味を抱いている大きな理由のひとつです。
エドガール・モランの一言がきっかけで
月永 『二重のまち/交代地のうたを編む』(画家で作家の瀬尾夏美と小森の共同監督作品)などを観ていて、小森さんの映画はドキュメンタリーという枠を超えた何かに挑戦されている感触があったので、小森さんが『ある夏の記録』を選んだと聞いてピッタリだと思いました。
本作の監督二人、ジャン・ルーシュとエドガール・モランのうち、ルーシュは映画監督としても著名で、短編も含めて120本近くの作品を残しています。対して、モランは映画監督ではなく、社会学者であり映画理論家でもあります。ルーシュは、第二次世界大戦に兵士として参加した後、土木エンジニアとしてニジェールに派遣され、そこで出会った人たちや土地の生活に魅了されます。それで今度は人類学者としてカメラを持ってニジェールに赴きます。先ほど小森さんも紹介されていたニジェールのカバ狩りや儀式の様子を撮った作品を、1950年代にパリで上映したところ、ゴダールやトリュフォーといったヌーヴェルヴァーグの作家たちから熱狂的な支持を得ました。特に『私は黒人』という作品は、ゴダールがかなり熱烈に批評を書いています。
ずっとアフリカで映画を撮っていたルーシュが、なぜ『ある夏の記録』ではフランスで撮ったのか。ここで重要になってくるのがモランです。ルーシュの友人であるモランが、「君はアフリカの人たちのことはよく知っているが、フランス人のことは知らないんじゃないか」と言ったそうなんです。それを受けてルーシュは「確かに、現代のフランスの若者たちや、フランスで働く労働者たちについて自分は知らないかもしれない。じゃあそれを撮ってみよう」と思い、撮り始めたのが『ある夏の記録』です。なので、ルーシュにとってはアフリカで未知の人々を撮っていたのと同じように、未知のフランス人たちを撮ったのがこの映画だと言えると思います。
シネマ・ヴェリテとは何か
月永 もうひとつ、短い時間で話せるか自信ありませんが、シネマ・ヴェリテとは何かということを語らなければならないだろうと思います。この講座のチラシでも本作は「シネマ・ヴェリテの金字塔」と書かれていますが、言葉の意味としては、フランス語でシネマが「映画」、ヴェリテが「真実」なので、日本語だと「映画=真実」とか「真実の映画」と訳されることが多いです。
もともと、1920年代にジガ・ヴェルトフというソ連の映画監督が手掛けていたキノ・プラウダというニュース映画のシリーズがあり、カメラによって現実を撮りながら、隠された深層心理というか、現実を再構築していく試みが行われていました。キノ・プラウダは、ロシア語で「映画=真実」という意味なので、シネマ・ヴェリテはキノ・プラウダのフランス語訳と考えていいのではないかと思います。本作の冒頭で「これは私たちによる実験だ」と言っていますが、ルーシュは映画監督として、モランは映画理論家として、フランスでキノ・プラウダを実践するならどうなるかを独自の方法で試したのが本作であり、シネマ・ヴェリテであると理解しています。つまり、シネマ・ヴェリテ=『ある夏の記録』である、と言っていいと思います。
ダイレクト・シネマとシネマ・ヴェリテの関係についてもお話したいと思います。シネマ・ヴェリテは先述したように、ルーシュとモランが本作で試みた実験を指すのに対し、ダイレクト・シネマは1958年にカナダのケベックで誕生した後、様々な形で継承されていきました。第4夜で上映された『セールスマン』もそのひとつですね。『ある夏の記録』は、同時録音と軽量カメラで撮られたフランス映画としては初期の作品ですが、ルーシュたちは本作をつくる上で、ケベックからミシェル・ブローという人を撮影監督として招いていています。彼はダイレクト・シネマを始めた人のひとりで、ルーシュとモランは彼から技術を学びながら本作をつくりました。ですから、両者は少し違うものではありますが、シネマ・ヴェリテはダイレクト・シネマの影響を強く受けていると言えます。
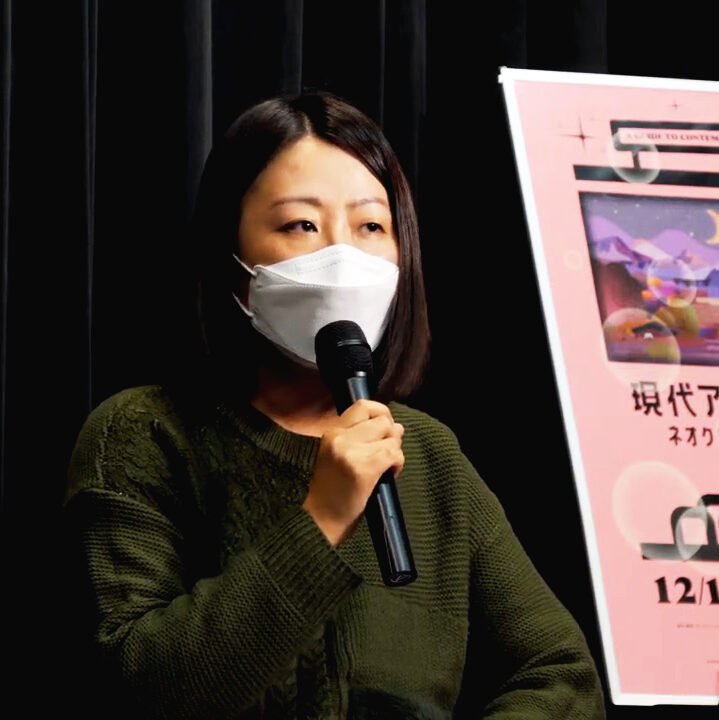
カメラを通して「本当の何か」を撮る
月永 最後に皆で試写を観ながら語る場面は、私も観ていて興奮しましたが、小森さんも被写体の人たちと一緒に映画を観て討論されたことはありますか。
小森 いえ、全くないんです。完成する前に確認のために観てもらうことはありますが、制作過程で観てもらって意見を聞きながら撮影していく手法は取り入れていません。でも、そういう作り方に憧れるというか、いいなと思っているんです。というのも、ルーシュが影響を受けたひとりに『極北のナヌーク』などを監督したロバート・フラハティがいて、フラハティは現地に住みこんで撮ったものを見せて議論し、演じ直しながら記録していく手法を実践しているんですよね。自分が撮るだけではなく、その土地の人に記録を返したいというか、撮られる側の何かを受け止めたいという気持ちがあって、こういうつくり方があり得ることに背中を押されます。

月永 すごく単純に言うと、シネマ・ヴェリテは真実を求める試みなわけですが、同時録音によって現実の音をそのまま録ること以上に、被写体の人の本当の生活や声を記録するために演出をしていくということだと思うんですね。そう考えると、小森さんと方法は違っても、本当の何かを撮るにはどうしたらいいかという点で通じているのかなという気がしました。
小森 そうだといいんですが…自分が見て、感じている状態をカメラでとどめておきたいと思ってもなかなかできないというか、ある状態を撮りたいと思ったときに、私はあまりやらないですが、演じ直してもらうようなことって起き得ると思うんですね。『ある夏の記録』でも生活風景が出てくるじゃないですか。その人の一日の始まりから終わりまでをカメラで撮っていますが、動きを止めてもらわないと撮れないようなところがあって、何かしら指示のようなものはあったんじゃないかなと思います。それでも、この人はいつもこうしているんだろうなと思えるのはなぜだろうと考えながら観ていました。マリルーがインタビューの後にパートナーと部屋から出ていくところはすごすぎて…。ああいう場面は当たり前に撮っているように見えて、すごく難しいと思います。
月永 あそこはすごく美しいですよね。ちなみに彼女はマリルー・パロリーニという人なんですが、あそこで一緒に映っている男性はジャック・リヴェットなんですよ。マリルーが、カイエ・デュ・シネマの事務所で秘書として働いているときに知り合ったみたいで、リヴェットの作品で一緒に脚本も書いています。演出をしたからこそリアルな風景が映るのは、ルーシュの映画にとってすごく重要なテーマだと思いますが、同時にドキュメンタリーとして観たときに不思議に思う人はいるかもしれないですよね。
フラハティの『極北のナヌーク』も、イヌイットの人たちを演出して撮っているので、本当にドキュメンタリーと言えるのかという議論もあります。本作も、これが本当に真実と言えるのか、演じているじゃないかといった意見があると思うんですけど、そのあたりはいかがですか。
小森 言い方が難しいですけど、演じているのがある意味前提というか、その人がその人らしくいられたり、自分で選択した姿を見せてくれる最低限の場はつくったうえで撮っていると思うので、その人の内面みたいなものを無理に引き出そうともしていない気がして。こんなにカメラが近くにいられる状態で、その人が自然にいることが写し取られていることも含めて、複層的にいろんなことが組み込まれているので、角度によっても見え方が違いますし、一回では見尽くせない作品だと思っています。
質疑応答
──インタビューで、どうすれば相手が自然に話せると思いますか。一般の人にカメラを向けるときに心がけていることはありますか。
…KBCシネマ、ユーロスペースより
月永 どうすれば自然な会話が引き出せるかは、いまだに模索中です。本作で面白いのは、どうやったって作意というかウソのようなものが生まれてしまうことで、相手に合わせて演じてしまうといったことも含めてその人だと思うんですよね。どういうふうにその人の「素」を引き出すかより、カメラの前で構えることも含めて現実として捉えていくことが大事なのかなと思います。
小森 状況にもよると思いますが、聞き手になる人が別にいたり、私も一緒に聞いているけど撮影もしているという中間の場所にいられるときの方が、撮りたいものに近いものが撮れている感覚があります。それが自然と言えるかはわからないですが。一般の方にカメラをどう向けるかは作品によって異なりますが、『二重のまち/交代地のうたを編む』の際は、自分たちがどういうものを撮りたいか、どういう人が話を聞きに来るかを、映ってくださる方に事前にお伝えしたうえで家にお邪魔して撮影させてもらっています。映画をつくるプロセス自体を被写体の方たちと共有しながらつくれた作品ではありました。
──試写を終えたルーシュとモランが「日常の真実とは違う次元の真実に到達した」「我々は前進した」と言っていましたが、お二人はこの言葉をどう受け止めますか。
…シネマテークたかさき、長野相生座・長野ロキシーより
小森 「到達した」と言っているところを撮しているのがまた…。その姿の方がよっぽど演じているようにも見えましたし、作為的であるとも感じました。前進なのかどうかわかりませんが、冒頭で名だたる作品と並んでカンヌ映画祭で受賞しましたみたいに見せていて(笑)、そこまで作品を作り変えてしまうところも面白いなと思いました。
月永 答えになるかわかりませんが、本作は映画史において大きな事件と言ったら大げさですが、それぐらい革命的な映画だったと思います。本作がドキュメンタリーかフィクションか戸惑うのも、撮影することによって、現実自体がどんどん変化していってるからですよね。カメラで撮影するという行為が、現実にこれほどの力を及ぼすことを問題提起した作品だと思うので、それがある意味で映画を前進させたと言えるのかなと思います。あと、本作がフィクションの中に現実を取り込もうとするヌーヴェルヴァーグの動きの中で生まれたことも重要だと思います。

これからのアートハウスについて
小森 コロナがあったからかもしれないですが、自分の住んでいる地域にフォーラム仙台やチネ・ラヴィータといった映画館があることで支えられているというか、担ってくれている役割がすごく大きいんだなと実感することが増えました。そのように、全国各地のアートハウスの役割が見えるようになってきている一方で、ただ映画を楽しむだけではいられない業界としての問題も明るみになってきている実感があります。なので、これからのアートハウスのあり方は、いままさに考えていかなければならないことだと思います。自分自身もそうですが、若い世代の人たちが関わりたいと思える後ろ支えになることを考えていかなければと思っています。どうしたらいいかは、いますぐには言えませんが、そういう場所に立っていると感じています。
(取材・構成=木村奈緒)
『ある夏の記録』
監督:ジャン・ルーシュ、エドガール・モラン
1961年|フランス|90分|モノクロ
パリ、1960年、夏。街ゆく人々に軽量16ミリカメラと録音機が問いかける。あなたは幸せですか? あるいは、愛、仕事、余暇、人種問題について…。作り手と被写体とが制作プロセスを共有することで、映画が孕む作為性や政治性が明らかになり、リアルとフィクションの概念が問い直される。映画作家で人類学者のルーシュと、社会学者で哲学者のモランによるシネマ・ヴェリテの金字塔。
小森はるか
映像作家
1989年生まれ。東京藝術大学美術学部先端芸術表現科卒業、同大学院修士課程修了。映画美学校フィクション初等科修了。2011年にボランティアとして東北沿岸地域を訪れたことをきっかけに、画家で作家の瀬尾夏美とアートユニット「小森はるか+瀬尾夏美」の活動を開始。翌2012年から陸前高田に拠点を移し制作を続け、現在は仙台在住。劇場公開作に『息の跡』『空に聞く』。瀬尾夏美との共同監督作『二重のまち/交代地のうたを編む』は、シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭のコンペティション部門で特別賞を、令和3年度文化庁映画賞で文化記録映画優秀賞を受賞。
月永理絵
エディター/ライター
1982年生まれ。出版社勤務の後、2014年よりフリーランスとして活動。個人冊子『映画酒場』などを編集・発行。『週刊文春』や『メトロポリターナ』など多くの連載を持ち、朝日新聞の映画評の執筆を担当。万田邦敏監督『愛のまなざしを』や、濱口竜介監督『偶然と想像』など、映画パンフレットの編集も多数手がける。2021年3月に開催された特集上映「映像作家・小森はるか作品集 2011-2020」の関連企画で、ほぼ全ての上映作品を解説。




