連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」(2)
2021年12月11日~17日、全国24のアートハウス(ミニシアター)で同時開催された連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」。
監督や脚本家、製作者、編集者等、多彩な講師陣による7日間のトークの記録を連載します。

連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」
第2夜 2021年12月12日(日)
連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」第2夜は、アキ・カウリスマキ監督の『マッチ工場の少女』(1990)を上映。講師は、『あのこは貴族』で現代の東京を舞台に出自の異なる男女の人生の交差を描き、多くの共感を呼んだ映画監督の岨手由貴子さんと、濱口竜介監督との共同脚本『ドライブ・マイ・カー』が第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞に輝いた映画作家/脚本家の大江崇允さん。実作者の視点から、カウリスマキ作品における芝居、セリフ、カメラワークなど、様々な側面について考察していただきました。
思い出深い監督であり、稀有な作品
岨手 今回、カウリスマキ監督の作品だったら何でも良いので上映してくださいとお伝えして『マッチ工場の少女』を上映していただきました。2002年に大学進学のために上京した翌年、『過去のない男』が公開されていて、カウリスマキ監督は東京で映画を観る喜びを知った頃の、思い出深い監督なんです。上京2年目から自主映画を撮り始めて、当時は一観客としてカウリスマキ作品を楽しんでいましたが、その後、映画を撮っていく中で、これはどうやって演出してるんだろうとか、どういうバランスでこんな作品ができるんだろうって、どんどん謎が浮かんできたんです。自分が監督した商業映画(『あのこは貴族』)が今年公開になったんですが、今だからこそ、自分にはカウリスマキ監督のような作品は絶対に撮れないことがよくわかります。
『マッチ工場の少女』は割と初期の作品ですが、それまでの作品は、男性の物語のイメージが強かったと思います。本作は主人公の女性・イリスが、ものすごく不幸な目に遭っていく話ですよね。女性が世間や運命にいたぶられる姿を見どころにしている作品もあると思いますが、本作はそこに観る喜びを全然感じません。彼女が不幸な目に遭うことが、この映画の楽しみ方ではないんです。むしろ、彼女がそういう運命に抗っていく姿こそが印象的なんです。
冒頭から、マッチを作る過程が延々と描かれます。観る人によっては何かの象徴と捉えるかもしれませんが、本作より前に撮られた『罪と罰』でも、食肉加工場で延々と働く労働者の姿が描かれていますし、マッチ工場のシーンは、彼女の働いている世界観を描いていると私は捉えました。その後、バスに揺られて本を読みながら通勤する彼女の世界が描かれますが、始まって13分間、会話がありません。セリフ量だけでなく、表情や身体の動きといった人物のアクションもすごく省略されて描かれているのに、彼女のその時の感情が伝わってきます。多くの人がその秘密はなんだろうと疑問を抱いたり、そこに魅力を感じたりするのではないでしょうか。
映画の終盤、イリスが植物園にしずしずと入っていって花を見て、ベンチに座って読書をするシーンがありますが、私はこのシーンが本当に好きなんです。というのは、冒頭の通勤バスでも読書をしていたように、彼女は本来そういう人間だったと思うんですね。内に秘めた彼女の世界がちゃんとあった。だけど、誰かに愛されたい、愛してみたい、必要とされたいという、ただ素直に持っている感情を発露したことで、結果的に人を殺すことになってしまいました。
植物園のシーンまでは、説明的ではないけど、彼女の感情が観客にわかりやすく伝わるように描かれていたと思うんです。あのシーンがあるから、私は彼女の感情のすべてがわかるわけではなくて、ただの観客の一人だったんだと思わされる。彼女がああやって一人で過ごす時間があるのとないのとでは、この映画は全然違うのではないかと思います。カウリスマキの作品には、観客が登場人物の行動について手に汗握ったり、なんで間違った判断をしちゃうんだって悔しがったりするわけではない、独特な距離感が初期作品から明確にあって、それが魅力につながっているのではないでしょうか。
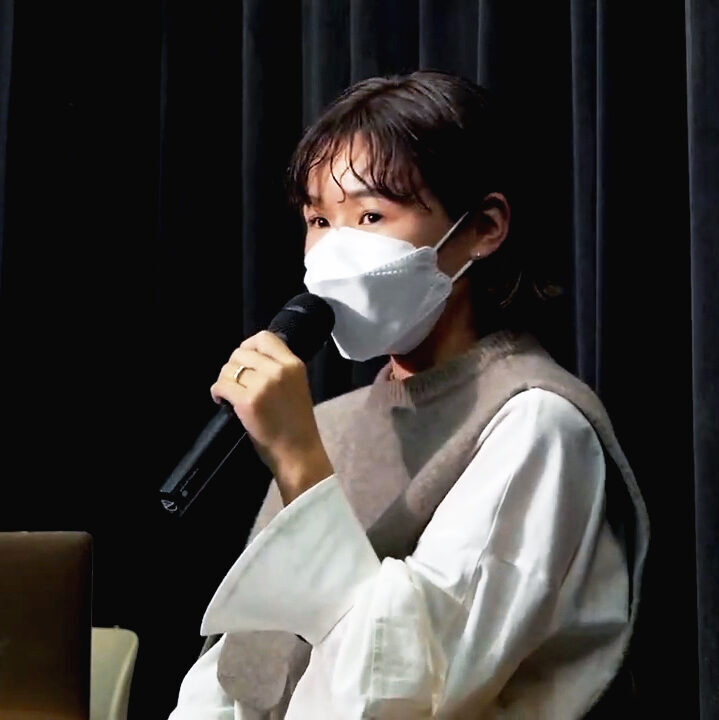
映画の原理に立ち戻った作品
大江 岨手さんがお話しされたことに同感ですが、僕なりの話をさせていただきたいと思います。男性を撮る監督というイメージがあるアキ監督の中で、本作はかなり特殊な映画だと思っています。それでいて、本質的には映画が表現するのが得意なことだけをシンプルにやっている構造に見えました。基本的に彼女の行動で映画が紡がれていて、映画の本質である「誰が何をした」を撮ることで、人物の感情が観客に伝わるようになっているのではないでしょうか。
アキ監督って「これをやるのが彼だよね」みたいなものがあると思っていまして。たとえば、なんだかわからない輩が出てきて主人公がボコられる。そして、主人公が捕まって出てくるという流れがほぼあるんですよ。あと、初期の頃は最終的に「楽園を目指してどこかへ行こう」みたいな結末の作品が多かったですが、本作はどれにも当てはまりません。要は、彼の得意なものを全部封印して、しかも追いかける実像を女性にすることによって映画の原理に戻ったというか、すごくシンプルな作品を作ることができたのかなと思っています。
彼女が幸せだったか不幸だったかについては、ユーモアがひとつキーワードになっているのかなと思います。不幸が重なったことで、イリスは人を殺してしまいますが、人を殺した後にバーでビールを飲んでいたら男に声をかけられる。今まではおしゃれを決め込んでも誰も声をかけてくれなかったのに。こういうところに監督のユーモアを感じるというか、人間ってこういう感じだよねと思える部分が描かれている。マッチ工場で作られた大量のマッチの一本じゃないけども、イリスが世の中のたった一人の人間であると同時に、その他大勢の一人でもあるといった目線でこのキャラクターを描いているのではないかと思いました。
もうひとつ、カメラが結果的にコメディの位置に置かれているカットがいくつかあって、それも本作が陰惨な物語になっていない理由のひとつとして考えられるかもしれません。ちょっと離れた位置にカメラを置いて、そこにポツンと立ってたり座ってたりすると、コミカルに見えるんですよね。イリスが、すごく悲しいことがあったのに、いきなりオレンジを食べ始めたりするところにも人間のおかしみを感じました。
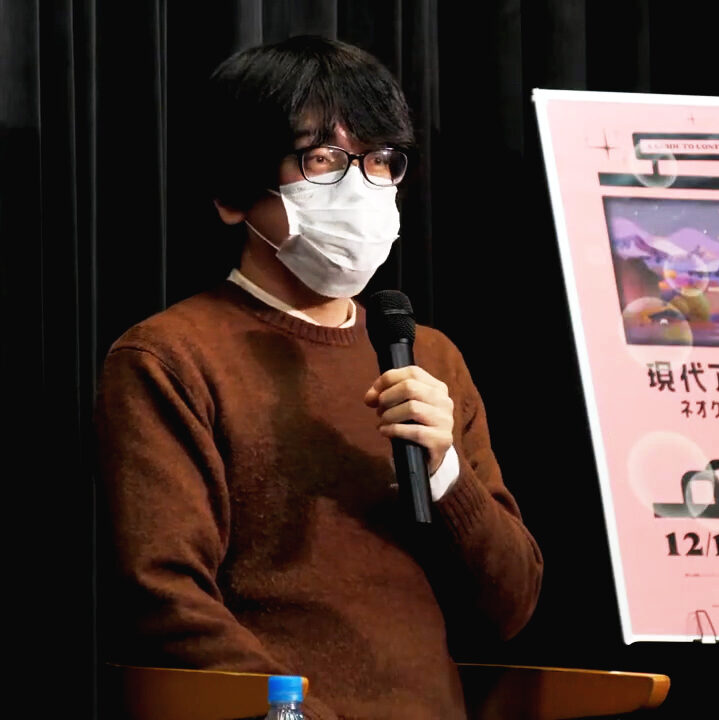
リアリティの追求ではない、人間の描き方
岨手 大江さんがおっしゃったように、モテようとしたときにはモテないけど、どうでもよくなってふっきれた途端モテ始めるって、女性にとってはあるあるだと思うんです。ある意味、解放されたことで人の目を引く感じになったのかもしれないですよね。
大江 男もそうですよ(笑)。僕は、イリスの常に黙々と歩く姿がいいなあと思いました。彼女自身に人生の目的があるわけではないんだけど、何か目的をもった女性に見えて。岨手さんは、お芝居で気になった点はありますか。
岨手 セリフもほとんどないし、表情でも語らないじゃないですか。でも何もやっていないわけじゃないんですよね。カットが切り替わる前にちょっとだけ表情が緩んだりする。モノローグで心情を全部説明していたら、そんなに表情を見ないと思いますが、語りすぎないからこそ注意して見るし、それによってスクリーンとコミュニケーションができるのも映画ならではの楽しみだと思いました。あと、人って無意識に顔を触りながら話したりするけど、それが全くないですよね。ある意味リアルじゃないというか。
大江 同感です。映画にしてもドラマにしても、リアリティのあるお芝居を追求されていることが多いと思いますが、アキ監督の作品を観ていると、必ずしもそれが正しくないんじゃないかと思わせられるというか、そこで言われているリアリティって僕の固定観念でしかないんじゃないかという気にさせられます。リアリティを追求することが悪いわけではないですが、人間を描くことって、実はそんなにちっぽけではない可能性があって、もっと他の方法もあるんじゃないかと思えるんですよね。
岨手 リアリティを追求すると絶対に属性と関わってくるじゃないですか。イリスで言えば、労働者階級の女性ということになりますけども、リアリティよりも寓話的な側面に軸足を置くことで、属性や時代性から一定の距離をとって、人間が本来持っている姿、欲望、感情にアクセスできるのかなと思いました。
大江 岨手さんの『あのこは貴族』にしても、あまり過剰なお芝居はされないですよね。ご自身は、どういう演出をされているんですか。
岨手 カウリスマキ監督みたいにやろうとは全然考えていないですね。『あのこは貴族』で門脇麦さんが演じた主人公のお嬢様は、本音を表に出さないキャラクターだったので、感情を爆発させるお芝居がなくてすごく苦しかったと門脇さんがおっしゃっていて、泣いたり叫んだりといったお芝居とは全然違う難しさがあるんだと思いました。

ロジックを超えた内面の変化の描き方
岨手 イリスが兄の家に身を寄せたとき、兄が家を出た後に音楽をかけるシーンがあって、次のシーンで殺鼠剤を買いにいくじゃないですか。でも、人が「よし、殺そう」って思うシーンを書くのって難しいんですよね。『あのこは貴族』でも、主人公が離婚を決意する流れを書くのがすごく難しかったんです。DVを受けたとか、わかりやすくひどいことをされたのであれば、その反射として離婚を決意するシーンは作りやすいんですね。だけど、わかりやすい着火剤がないのに長年蓄積した何かが爆発するときに、どうやったら説明的にならずに納得感があるように表現できるのか。ロジックとは違うものなのかなと思います。
大江 世の中で起こってることって、そんなに理詰めではないですもんね。本作は、イリス役のカティ・オウティネンによると、少なくとも俳優にとって脚本という脚本はなかったそうです。だからこそ、こういうシーンを撮ることができたのかなと思います。脚本って要は設計図ですから、現場で何をしたらいいかわかるように書くわけですが、それが必ずしも映画にとって良いとは言えなくて、きっちりした脚本があったら、こんなにもダイナミックな物語は描けないので一長一短ですよね。
岨手 映画のプロデューサーから聞いたんですけど、お知り合いの方が仕事で疲弊していたときに、新宿駅でギャルの女の子がすごく楽しそうに歩いてくるのを見て「あ、この仕事やめよう」と思ったそうなんです(笑)。その感じはすごくよくわかると思って。心が切り替わる瞬間って必ずしも直接の着火剤によるものじゃないというか。本作で言うと、狭くて暗い色彩の部屋から、明るくてモダンな兄の部屋に移ったことも大きいと思うんですよね。あれだけで割と納得して彼女の行動を追っていけました。
質疑応答
──序盤でセリフが極端に少ないのはなぜだと思いますか
…京都シネマ、フォーラム山形より
大江 必要なかったからだと思います(笑)。実はアキ監督は、もともと脚本を結構書いていて、その中でセリフもたくさん書いてたらしいんですよね。それがいつの間にか音楽が代わりに語ってくれるようになったので、セリフをどんどん削っていったと言っていて。でも削ぎ落としたぶん、細かいセリフひとつひとつにこだわっていると思いました。
岨手 そうですよね。イリスが妊娠を伝えた手紙と、その返事の内容の差を見ても、言葉に対してこだわりがあることがよくわかります。
──1989年の天安門事件のニュースが何度も流れますが、なんのメタファーだと思いますか
…シネマ尾道、KBCシネマ、フォーラム山形より
岨手 私が読んだ監督のインタビューでは「映画は単なる娯楽で終わらせてはダメだと思って作っている。(事件などの出来事を)忘れていってしまうから自分の作品の中に残しておきたい」と言っていました。「自分の作品にホームレスが登場しなかったら、自分の顔を鏡で見れない」みたいなことも言っていて、物語上意味がある差し込みではないけど、そういう人や出来事がこの世界に存在するという前提があるだけでも全然違うと思います。
大江 労働者階級の人々を描くことが多い作家ですが、民衆の怒りみたいなものをただ表現したかったということではない気がしています。なぜかと言ったら、ニュースを見ている母親と養父は、あまり興味を持っていないように撮っているからです。そうすることによって、これはただのひとつのニュースだけれども、記録として残っていると。そういう二重三重の意味合いに包まれている表現ではないかと思いました。
──大江さんから本作は「映画が得意な表現をやっている」というお話がありましたが、お二人は映画が得意な表現ってどんなことだと思いますか
…シネ・ヌーヴォより
大江 「人が行動して、それを見る」ことだと思います。小説は形容詞を描けますが、映画は形容詞を描けないんです。「美しい」を描きたくても、百人百通りの「美しい」があるので必ず一致はできないんですね。じゃあ映画で一致できるのは何かと言うと、「人が何かをした」です。この映画だと、イリスが理由があって犯罪をして捕まってしまうという彼女の行動を撮っているわけです。
岨手 原作モノを脚本化すると、小説と映画でできることが全然違うって思いますね。カウリスマキ作品で言うならば、セリフや音楽のバランスの付け方で全く違う作品になっていくところが、彼の作品ならではの楽しみ方じゃないかなと思います。セリフは一切なしでテロップと音楽の歌詞だけで語っている作品もあれば、会話劇っぽい作品もありますし、それは映画だからこそできることですね。

これからのアートハウスについて
岨手 『マッチ工場の少女』や、第1夜で深田監督が紹介してくださったキアロスタミ監督の作品がネオと言いつつ、もうクラシックなんだって、時の流れを感じて衝撃を受けました。でも若い観客の方からしたら、自分が生まれる前の作品だったりするので当然なわけで、長い歴史の中でどうやって映画を楽しんでいくかを知ることができる、すごく良い講座だなと思いました。今日のために読んだインタビューで、ジム・ジャームッシュとカウリスマキが友だちだと書いてあって、自分が映画を一番観ていた時期の監督たちが友だちなんだと思うとすごく嬉しくて気分があがりました。若い観客の方もそういう楽しさをどんどん味わってほしいなと思います。
(取材・構成=木村奈緒)
『マッチ工場の少女』
監督・脚本:アキ・カウリスマキ
1990年|フィンランド|69分|カラー
マッチ工場で働くイリスは、母と義父を養っている。ある日、給料でドレスを衝動買いしてしまった彼女は、義父に殴られ、母からドレスの返品を命じられる。ついに我慢できなくなった彼女は、家を飛び出しディスコで出会った男と一夜を共にするが、その男にも裏切られ…。何の変哲もない娘のどん底の人生を淡々と描き、絶望的な状況になぜか笑いが込み上げてくるアキ・カウリスマキ映画の真骨頂ともいえる一作。
岨手由貴子
映画監督
1983年長野県生まれ。大学在学中に自主制作映画を始め、09年、文化庁委託事業若手映画作家育成プロジェクトndjcで『アンダーウェア・アフェア』を製作。15年、長編商業デビュー作『グッド・ストライプス』が公開。本作で第7回TAMA映画賞最優秀新進監督賞、2015年新藤兼人賞金賞を受賞。21年、山内マリコの同名小説を映画化した『あのこは貴族』が公開。本作で第13回TAMA映画賞最優秀作品賞を受賞。
大江崇允
映画作家/脚本家
1981年、大阪府出身。近畿大学で演出家の大橋也寸氏よりフランスの演技システムであるルコック・システムを学び、卒業後も演出や俳優として舞台作品に携わる。その後、映画制作を始め、監督・脚本として活動。監督作品に『美しい術』(09)、『適切な距離』(11)などがある。また、ドラマでは演出「君は放課後、宙を飛ぶ」(18/TBSサービス・東映)、脚本「恋のツキ」(18/TX)など。『ドライブ・マイ・カー』では、脚本を手掛けた濱口竜介監督と共に、第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞に輝いた。
現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 vol.2
2021年12月11日(土)-17日(金)
全国24館で実施
企画・運営:東風 企画協力・提供:ユーロスペース
協力・提供:アイ・ヴィー・シー/アンスティチュ・フランセ日本/グッチーズ・フリースクール/コミュニティシネマセンター/シネマテーク・インディアス/ノーム
文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業
https://arthouse-guide.jp/




