上映作品『書かれた顔』(ダニエル・シュミット|1995)
トーク:甫木元空(映画監督/Bialystocks)×須藤健太郎(映画批評家)
巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」(1)
「現代アートハウス入門」の第3弾として、2022年10月~12月に行われた巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」。
上映に合わせて行われた監督や研究者等々、多彩な講師陣によるトークの記録を連載します。

現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑 (1)
『書かれた顔』(監督:ダニエル・シュミット|1995年)
トーク:甫木元空(映画監督/Bialystocks)× 須藤健太郎(映画批評家)
2022年10月22日 東京|ユーロスペース
巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」、東京・ユーロスペースの第1夜は、スイスのダニエル・シュミット監督が日本で撮影した『書かれた顔』(1995)を上映。講師は、2022年、バンドBialystocksでメジャーデビューを果たし、新作映画『はだかのゆめ』が封切られたミュージシャン/映画監督の甫木元空さんと『評伝ジャン・ユスターシュ:映画は人生のように』など、骨太な著書を持つ映画研究者の須藤健太郎さん。ドキュメンタリーと言えど、虚実を往復し黄昏時に誘い込むシュミットの妖しい世界に斬り込みました。
身振りが空間を変容させる
須藤 『書かれた顔』は日本のアートハウス文化にとって重要な作品です。1982年、アテネフランセ文化センターで開催された「ダニエル・シュミット映画祭」が大成功を収め、ダニエル・シュミットという監督は日本の80年代シネフィル文化を象徴する存在になります。そして、アートハウス文化が熟成するとともに、日本のシネフィルとシュミットとの関係が育まれていった結果、1995年にユーロスペース製作で『書かれた顔』という映画が作られるにいたる。堀越謙三さんの自伝『インディペンデントの栄光』(筑摩書房)でもたっぷり語られていますね。まず、甫木元監督が今回この作品を選ばれた理由をお話しいただけますか。
甫木元 「嘘に開き直ったドキュメンタリー」を選びたかったんです。カメラが置かれただけで、その場は自然ではなくなっているし、居る人たちもカメラによって演じちゃっているかもしれない。そこに映画の秘密が隠されているような気がするんです。それに、それまで日本テレビの「金曜ロードショー」みたいなものでしか映画と接してこなかった僕が、初めて観たアートハウス系映画が『書かれた顔』なんですよ。多摩美術大学の映像演劇学科の授業で、舞踏家の大野一雄さんが船上で舞踏する場面だけみせられて「どういう映画なんだろう」と疑問に思ったのが、僕の映画体験の始まりなんです。それから全編を観て、映し出されるすべての動作がアクションのようであり踊りのようで、それらの動作をまるで一筆書きのようにつなげるだけで映画って成立しちゃうんだな、と衝撃を受けたんです。
須藤 いま動作や身振りのお話が出て、すごく嬉しい気持ちです。僕も同じことを考えていました。坂東玉三郎さんが「ある空間が与えられたときに、そこにいるだけでその空間を別の空間に変容させる力をもった人たちが俳優なんだ」ということをこの映画の中で言っていますよね。『書かれた顔』は、存在するだけで空間を変容させてしまうというすごい力を持った人しか出てこない映画で、ふとした身振りによって空間がガラっと変わる、そういう出来事に観客が立ち会ってしまう映画ですよね。
甫木元 『書かれた顔』を観ていると、普通の映画だったら編集段階で削ぎ落とされてもおかしくないような身振りから、感情を読み解こうとさせられたり、起こったことがなんだったのか想像させられたりします。だから、僕は4~5回目の鑑賞なんですけど、毎回違ったことを想像させられて観るごとに違った映画に思えてくるんです。

トワイライト——失われつつあるものを撮る
須藤 『書かれた顔』のなかで玉三郎さんが演じる劇中劇のタイトルが「黄昏芸者情話(トワイライト・ゲイシャ・ストーリー)」。「黄昏」「トワイライト」というのが『書かれた顔』のキーワードになっています。武原はんさんがバイバイと手を振ってみせたり、杉村春子さんが最後に舞台袖に去っていく姿をみせたり……、消えてゆく前の最期の姿を撮る(ちなみに、甫木元さんの『はるねこ』で森の中に人が消えていくとき、みんな一度振り返ってこちらを見ますけど、あれは『書かれた顔』の杉村春子さんの身振りを想起させますね)。実際、出演されている101歳の芸者・蔦清小松朝じさんはこの映画の公開翌年(96年)にお亡くなりになっています。武原はんさんも人前で踊ったのはこれが最後になったと言われています。
甫木元 人が最後に何かをした瞬間を捉えてしまう、とか「映画を撮る」という行為は不思議な因果を背負ってしまうことがあると思うんです。肉体が滅して幽霊になってゆく人たちの受け皿になることがある、というか。
須藤 失われつつあるものを撮る。玉三郎さんはこの時期、自分の舞踊を35ミリフィルムで記録しているんです。つまり当時、本人にとって一番良い時期だから自分の芸や姿を残しておきたいという意識があったのかもしれません。この映画への出演を承諾したのもそれと無関係ではないように思います。玉三郎さんは、他の高齢の出演者とは違って、当時はまだ40代ですけど、今のこの芸の姿が失われる前にカメラで記録した、という意味では共通しているのかもしれません。
甫木元 『書かれた顔』に登場する歌舞伎の場面も、数百年間という長大な時間のなかで、一代限りで消えてしまわないよう、人から人へ伝承されてきた身ぶりのある一時期が捉えられている、ということなんですよね。シュミットはオペラの演出もしていますが、伝統として継承されていくものに興味を持っていたと思うんです。
須藤 『書かれた顔』では玉三郎さんが演じる演目がいくつか映されますが、なかでも「鷺娘」が中心的に扱われています。興味深いのは、冒頭で映されるのは「鷺娘」のラストで、つまり死ぬシーンから始まるんですね。そして最後にもう一度このシーンに戻ってくる。ひとは死ぬ直前に人生で刻んだ記憶を走馬灯のように振り返ると言われますが、走馬灯さながらにモチーフがちりばめられた断片的な映像が現れる映画という気がします。そのモチーフの連関が観るたびに違ってみえるのが、面白いんです。
物語るだけが映画じゃない
須藤 はじめに甫木元さんがおっしゃっていた「一筆書き」という言い方は面白いですね。この『書かれた顔』という題名はロラン・バルトの 日本論『記号の国』(みすず書房)からとられているんですが、バルトは日本文化の特徴のひとつを「アラ・プリマ」という絵画技法になぞらえていて、要するにこれって「一筆書き」みたいなことなんです。バルトは「書かれた顔」と題した章で、特に歌舞伎の女形について書いています。女形というのは女になることではなくて、女という記号を組み合わせることだ、女を「表象する」のではなく、女を「意味する」のだと言っています。「エクリチュールとは観念の身振りからなる」というマラルメの言葉がありますが、バルトはそれをもじって、「女形は「女」という観念の身振りそのものだ」とか言うわけです。『記号の国』は、日本のことをよく知りもしないで、と批判もされた本ですが、『書かれた顔』を観ると、玉三郎さんがまったく同じことを言っています。武原はんさんも杉村春子さんも、女であるということを「材料」として使うことができた偉大な表現者だと。バルトの用語で「記号」と言われているのは、玉三郎さんがいう「材料」と同じことですよね。
バルトの「書かれた顔」という表現も面白いんですが、バルトは、日本の演劇では顔は「描かれている(化粧されている)」のではなく、「書かれている」と言っています。白粉が塗られると、顔が白紙のページになる。そこに黒で書き込みがなされる、と。バルトはさらに議論を展開して、黒い目は白い顔の上にあるのではなく、顔を穿つ窪みとして目の黒があると言っていて、僕はこの箇所がずっとよくわからないでいたのですが、『書かれた顔』の大野一雄さんを見たときにバルトの形容を思い出し、「こういうことか」と思ったりしました。
甫木元 いまのお話を聞いていて思ったんですが、昔は照明機材も充実していなかったので、暗闇の中で光を強く反射させ顔を目立たせるために俳優は白地を塗ったのだとは思うんです。けれど、僕は白く塗ることで俳優が「何かを書き込める存在」になっていくことに惹かれます。『書かれた顔』で大野さんが踊る場面を観ると、なんだか背景に目が行くんです。大野さんが顔を白く塗ってその場に立つ。画面の真ん中に「無」の存在があるから、背景にある船や鳥たちが引き立つんだと思うんですよ……。そうした大野さんをはじめ、さまざまな人たちの身振りがつなげられて、一筆書きのように、踊りを踊るように、音楽が演奏されるように、後戻りせずに展開していって、最初とは違った場所にたどり着く映画が存在している……。そのことに、大学に入りたての僕は衝撃を受けたんです。そこで初めて「物語るだけが映画じゃないんだ」と認識できました。『書かれた顔』を観終わって、思い出すのは物語ではなく身振りなんです。映画体験の初めにそういう体験ができたのはよかった、といまでも思います。

質疑応答
——『書かれた顔』を考えるにあたって、ドキュメンタリーの虚構性や演出についてどのように考えられますか。
甫木元 僕は、ドキュメンタリー映画もフィクション映画も、映画には総じて「ホントっぽいことが記録されている」と思っています。表現する行為には「嘘をつく」ということが前提とされているはずで、ドキュメンタリーだけが真実を伝えているということでもないだろうし、実際、虚構のほうが事実の核心を突いてしまうこともありますよね。
須藤 冒頭から舞台上の玉三郎さんを客席の玉三郎さんが見ている、という、映画ならではの「切り返し」の虚構性からはじまる映画です。そして「黄昏芸者情話」という虚構の劇映画が挿入される。これは玉三郎さんが「演りたい」と言ってつくられたパートなんだそうです。つまり、この部分はフィクションではあるのですが、カメラの前にいる被写体の頭の中にある想像の世界という意味では、この部分も玉三郎さんを捉えたドキュメンタリーなわけです。
——甫木元監督の恩師、青山真治監督は『書かれた顔』の大野一雄パートの助監督を務められました。青山監督は甫木元監督に「踊りは撮れない」とおっしゃったそうですが甫木元監督ご自身、踊りはどうやったら撮れると思いますか。
甫木元 青山さんは、大野一雄さんを撮る場面で移動撮影用のレールを運んで大変だったと聞いています。その撮影に立ち会って、青山さんが何を考えたのかまではわかりません。ただなんでもかんでも撮れると思うなということはよく言っていました。自然現象や自分が直に感じ体験したことすべてを映画にまとめることはできない。現場で起きたことには絶対にどこかで嘘をつかなければならない。青山さんが「撮れない」と言っていたのは、撮ろうとしても撮れないことがあるということを認識して撮影しなければならないということなのかな、と僕は思っています。一方、僕が考えるのは、ジャン=リュック・ゴダールの『ワン・プラス・ワン』じゃないですけど、ダンスを撮ったカットにまったく違うものを撮ったカットをつなげることで、両方が浮き立ってくることがあるのかな、ということだったりします。けれども、謎は深まるばかりで確かな答えはまだ見つかっていません(笑)。
ふたりのアートハウス讃歌
甫木元 映画を成り立たせるものを、実験的に遊んでいるのがドキュメンタリー映画なんじゃないか、と僕は思っています。そういう映画の可能性の広がりを、知らない人たちと一緒にスクリーンで観ることはかけがえのない体験になるはずです。今日は久々に最前列で観たんですが、後ろでどんな人たちが観ているんだろうと多くの人たちの存在を背負いながら観た気がしています。
須藤 僕は、「家で映画を観るのはよくない、絶対にスクリーンで観るべきだ」とまでは思わないんですが、映画に限らず「出来事に立ち会う」って重要なことですよね。たとえば今日も、みなさんと一緒に新たに4Kで甦った『書かれた顔』を観たわけですが、それを30年前に製作したユーロスペースの劇場で観た、ということが大事なんですよね。ほかの映画館ではこういう感動は得られなかったはずです。
(取材・構成=寺岡裕治)
『書かれた顔』
原題:The Written Face
監督:ダニエル・シュミット|1995年|スイス、日本|89分
歌舞伎界で当代一の人気を誇る女形、坂東玉三郎。「鷺娘」「積恋雪関扉」といった舞台や、芸者に扮した彼を2人の男が奪い合う劇「黄昏芸者情話」が挿入され、玉三郎の秘密へと観る者を誘う。俳優の杉村春子や日本舞踊の武原はんの談話、現代舞踏家の大野一雄の舞いなども。現実と虚構さえもすり抜けていくシュミットのスイス・日本合作となった本作では、青山真治が助監督を務めた。

『書かれた顔』4Kレストア版、全国順次公開中!
甫木元空 ほきもと・そら
映画監督/Bialystocks
1992年生まれ。2016年、監督・脚本・音楽を務めた長編映画デビュー作『はるねこ』がロッテルダム国際映画祭コンペティション部門に選出、イタリア、ニューヨークなど多数の映画祭に招待された。映画制作だけでなくMV制作や音楽活動も行い、2019年には四人組バンド「Bialystocks」を結成。2022年11月、監督最新作『はだかのゆめ』が公開された。
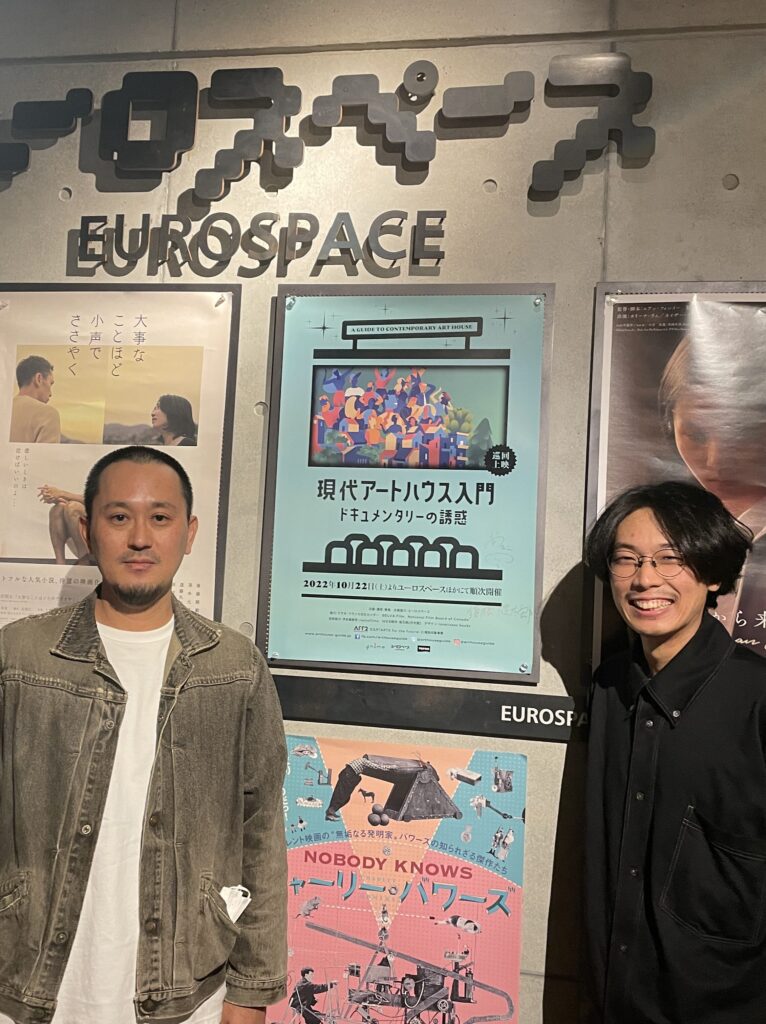
須藤健太郎 すどう・けんたろう
映画批評家
1980年生まれ。パリ第三大学博士課程修了。博士(映画研究)。専門は映画史、映画批評。現在、東京都立大学人文社会学部助教。著書に『評伝ジャン・ユスターシュ: 映画は人生のように』。訳書に、ニコル・ブルネーズ「映画の前衛とは何か」(現代思潮新社)、「エリー・フォール映画論集 1920‐1937」(ソリレス書店)などがある。
現代アートハウス入門
「現代アートハウス入門」は、若い世代に〈アートハウス〉(ミニシアター)の魅力を伝えようと、2021年にはじめられた企画。第1~2弾 連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜」では、〈アートハウス〉の歴史を彩ってきた傑作を「ネオクラシック(新しい古典)」と呼び、東京・ユーロスペースを拠点に全国の映画館で、7夜連続日替わりで上映。気鋭の映画作家が講師として登壇、各作品の魅力を解説。
2022年秋~冬に行われた第3弾、巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」では“ドキュメンタリーと呼ばれる方法で作られた映画”にフォーカスし、18名の気鋭の映画作家に「若く新しい観客に映画の魅力を伝えるために5本の“ドキュメンタリー映画”を観せるとしたら、どんな作品をセレクトしますか」というアンケートを実施。その結果をもとに以下の7作品を巡回上映した。
巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」上映作品
ルイジアナ物語 監督:ロバート・フラハティ|1948年|アメリカ|78分
人間ピラミッド 監督:ジャン・ルーシュ|1961年|フランス|90分
1000年刻みの日時計 牧野村物語 監督:小川紳介|1986年|日本|222分
セザンヌ 監督:ジャン=マリー・ストローブ、ダニエル・ユイレ|1989年|フランス|50分
書かれた顔 監督:ダニエル・シュミット|1995年|スイス、日本|89分
SELF AND OTHERS 監督:佐藤真|2000年|日本|53分
物語る私たち 監督:サラ・ポーリー|2012年|カナダ|108分
現代アートハウス入門ウェブサイト https://arthouse-guide.jp/







